「あとでやろう」が未来を止めている?
僕:「あー…また“あとでやろう”って言い訳して、結局なにもできなかった…」
しおり:「その“あとで”って、いつ来るんだろうね?」
僕:「うっ…確かに。でも、やる気が出ないと動けなくてさ…」
しおり:「実はね、“やる気が出たから動く”んじゃなくて、**“動いたからやる気が出る”**んだよ」
僕:「え、それって…逆じゃないんだ?」
しおり:「うん。千田琢哉さんの**『すぐやる力で差をつけろ』**には、
“すぐ動ける人が、なぜ人生を変えられるのか”が、ぎゅっと詰まってるんだ」
僕:「後回し癖から卒業したい僕に、ぴったりの一冊かも…!」
しおり:「じゃあ一緒に、“すぐやる力”を身につけて、人生の流れを変えていこう!」
なぜ「すぐやる力」が人生を動かすのか?
評価とチャンスは“速さ”で決まる
僕:「“仕事ができる人”って、どうしてあんなに周りから評価されるんだろう…?」
しおり:「それ実は”スピードが鍵”なんだよ。“すぐやる人”って、信頼も評価も自然と集まってくるの」
僕:「えっ、でも能力とかスキルの話じゃないの?」
しおり:「もちろんスキルも大切。でもね、たとえば連絡に即レス、頼まれたことをすぐやる、それだけでも『この人は信頼できる』って思われやすいの」
僕:「確かに、先輩でいるなあ。いつも納品も早いし、自然と仕事も集中してる」
しおり:「それに、“ピッとひらめいたらパッと動く”――“ピッパの法則”って知ってる?」
僕:「語感はかわいいけど…内容はすごいな(笑)」
しおり:「思いついたらすぐ動く。その瞬発力が、成功者たちに共通しているの。
頭の良さよりも、“すぐやる力”が、チャンスを引き寄せる本質的なスキルなんだよ」
仕事の成果は「スタートの早さ」で差がつく
僕:「でも、早くやるって言っても、焦ってるだけじゃない?」
しおり:「それ、よく誤解されるんだけど、“すぐやる人”は焦ってるんじゃなくて、ただ早く始めてるだけなんだよ」
僕:「え、つまり“落ち着いてるのに早い”ってこと?」
しおり:「そうそう。たとえば、朝早く起きて人より先に仕事を始めてる人とかね。
“スタートが早い人”は、結果的に余裕を持って終わらせられるから、仕事の質も高くなるの」
僕:「100m走だってスタートが早ければ有利だし、納得かも」
しおり:「そう。千田さんも言ってるけど、“フライングが当たり前”ってくらいでいいの。
仕事の世界では“早すぎて怒られる”ことって、ほぼないからね」
僕:「なるほど。早く終わらせておけば、万が一ミスしてもやり直す時間あるしなあ」
しおり:「その通り。“すぐ始めてすぐ終わらせる”って、ミスも防げて自分も楽になる。
“速さ”は、安心を生む最高のリスクヘッジでもあるんだよ」
「後でやる」は脳に負担をかけていた?
未完了タスクが集中力を奪う
僕:「最近、集中力が続かなくて…やる気はあるのに頭がモヤモヤするんだよね」
しおり:「それ、“後回しにしたタスク”が脳に溜まってるせいかもしれないよ」
僕:「えっ、やってないことが集中力に影響するの?」
しおり:「うん。脳ってね、“終わってないこと”をずっと覚えてようとするんだって。
まるで、散らかったデスクトップに100個のファイルが放置されてる状態」
僕:「うわぁ、僕のパソコンそのまんまだ…」
しおり:「そうなると、目の前の仕事にも集中できないし、知らないうちに脳が疲れていっちゃう。
だから、“後でやろう”って溜めるのは、思ってる以上にダメージが大きいんだよ」
「いつやるか」を決めるだけで脳が軽くなる
僕:「でもさ、全部今すぐやるのって無理じゃない?忙しいし…」
しおり:「もちろん全部は無理。でもね、“今できないなら、いつやるかだけ決める”。
それだけで、脳は安心してストレスが減るんだって」
僕:「たしかに、予定をカレンダーに入れた瞬間、気がラクになることある!」
しおり:「そうそう。“すぐやる”か“日時を決めておく”かの二択が、タスク管理の基本なんだよ」
僕:「つまり“やらなきゃ…”って思い続けるのが、一番よくないんだね」
しおり:「うん。頭の中で悩みをループさせるより、“完了させる”ことで脳は軽くなるんだよ」
「すぐやる人」だけがチャンスをつかむ理由
行動の速さは“本気度”の証明
僕:「仕事ができる人って、なんであんなにチャンスをもらえるんだろう?」
しおり:「それはね、“すぐやる”という行動が、その人の“本気度”を物語ってるからなんだよ」
僕:「本気度…?スピードと関係あるの?」
しおり:「あるある。たとえば、連絡に即レスしてくれる人って“信頼できる”って感じない?」
僕:「わかる!頼んだ資料をすぐ出してくれる人にも、安心して仕事をお願いしたくなる」
しおり:「それ。スピードって、言葉以上に“この人は本気でやる気ある”って伝える手段なんだよ。
だから、チャンスは“すぐやる人”に集中するんだ」
質より“スピード”が求められるときがある
僕:「でも、早いだけで雑な仕事になっちゃったら逆効果じゃない?」
しおり:「もちろん質も大切。でもね、仕事の現場では“早く出してもらえれば、あとで直せる”ってケースも多いの」
僕:「あぁ…締め切りギリギリだと、ミスしても直す時間がないもんね」
しおり:「そう。だから“早く出す”って、それだけで相手への配慮にもなるんだ。
ミスがあっても、余裕を持って直せるから、結果的に全体の仕事の質も上がるんだよ」
僕:「なるほど…。速さ=相手への思いやりか」
しおり:「その通り。“すぐやる”って、自分のためだけじゃなく、周りへの信頼づくりにもなる行動なんだよ」
行動してから質問せよ
動かない人の質問は抽象的
僕:「この前、新しい業務でわからないことがあって、質問しようと思ったんだけど…うまく聞けなくて」
しおり:「うん、それって**“まだ何も手を動かしてない状態”だったんじゃない?**」
僕:「う…バレた」
しおり:「(笑)実はね、まだやっていない人の質問って、ふわっとしてて抽象的になりがちなんだよ。
“なんとなく不安”“どこがわからないかもよくわからない”って状態だと、聞かれても答えづらいでしょ?」
僕:「確かに…“とりあえず聞いてみる”みたいな質問してたなぁ」
しおり:「だからこそ、まずは一回やってみることが大事なんだ。
やってみたら、“ここが分からない”ってピンポイントで聞けるようになるから」
行動が質問の質を引き上げる
僕:「たしかに、やってから質問すると、めっちゃ具体的に聞ける」
しおり:「そうそう。しかもね、質問の質が高い人って、“やってる人”ってすぐ分かるの」
僕:「僕も“ちゃんと調べてきたんだな”って感じる質問、されたことあるかも」
しおり:「千田さんも書いてたけど、仕事においては“具体的じゃない質問は、意味がない”ってこと。
そして、**“1つやった人だけが、1つ質問する資格がある”**っていう名言もあるんだよ」
僕:「質問って“準備のない人の逃げ”にもなり得るんだな…」
しおり:「そう。だから、まず動く → それでも分からない → そこで初めて聞く
この順番が、結果的に最短ルートになるんだよ」
決断の速さが人を動かす
優柔不断は信頼を失う
僕:「上司のAさんって、いつも判断に時間がかかって、現場が止まっちゃうんだよね…」
しおり:「それ、“決断できない人”って見なされて、部下からの信頼を失いやすいんだよ」
僕:「え、決断ミスより、遅いことの方がまずいの?」
しおり:「うん。千田さんも、“上司は決断を間違えるからじゃなく、決めないから嫌われる”って書いてる。
つまり、迷ってばかりの人には、誰もついてこないってことだね」
僕:「あ…デートで“何食べたい?”って聞かれて1時間迷ったときの彼女の顔、思い出したわ…(笑)」
しおり:「(笑)あれも“即決してくれた方が頼もしい”って思われる典型例かもね」
決断力は“自分の軸”で鍛えられる
僕:「でもさ、即決って言われても、迷うときってあるじゃん?」
しおり:「もちろん。でもね、“迷わない人”って、自分の中に“決断の軸”を持ってるんだよ」
僕:「軸かぁ…。例えばどんな?」
しおり:「たとえば、“今だけじゃなく将来得する方を選ぶ”とか、“好きな方を選ぶ”とか。
千田さんは、“自分は好き嫌いで全部決めてる”って言ってたよ」
僕:「それ、潔いな…!(笑)」
しおり:「大切なのは、“軸があること”。それがあるから、迷っても自分なりの正解が出せるようになるんだ」
僕:「じゃあ、僕も“何を大事にしたいか”をはっきりさせておくのが大事なんだね」
しおり:「うん。“即決できる人”は、いつも判断の準備ができている人なんだよ」
「すぐやる人」になる3つの環境づくり
① 行動力のある人に囲まれる
僕:「“すぐやる”って、習慣にするの難しそう…意志の力だけじゃ無理かも」
しおり:「それ、正直に言って大正解。
人は“意思”より“環境”に強く影響される生き物なんだよ」
僕:「あぁ…たしかに。周りがダラダラしてると、自分もサボりたくなるし…」
しおり:「その逆もあってね。行動が早い人のそばにいると、自分の“普通”も自然と引き上がるんだよ。
ジム・ローンって人が、“あなたは最もよく過ごす5人の平均である”って名言を残してるの」
僕:「じゃあ、“すぐやる人たち”と一緒にいれば、僕も自然とそうなれるってことか!」
しおり:「そう。今の時代はSNSやコミュニティで、“なりたい自分像”の人たちに近づきやすいから、
自分から環境を選びにいくといいよ」
② 気が散らない作業環境をつくる
僕:「でも僕、部屋が散らかってて、ついスマホいじっちゃって…集中できないのも原因かも」
しおり:「それ、まさに“すぐやる”を阻む大きな敵!
物理的な環境が散らかってると、脳も散らかりやすくなるんだよ」
僕:「うっ…デスクの上にお菓子、雑誌、未処理の書類が…」
しおり:「まずは、今取り組んでいる作業に必要なもの以外は全部どけること。
あと、スマホは目に入らない場所へ!」
僕:「スマホって、机にあるだけで集中力が下がるって話もあったよね」
しおり:「そう。“あるだけで”ダメなの。集中環境の設計は、意志より仕組みで整えることがカギだよ」
③ 退社時間を決めて仕事にメリハリをつける
僕:「最近、なんとなく残業しちゃって、ダラダラしがちで…」
しおり:「それも改善できるよ!
“退社時間を先に決めておく”だけで、仕事のスピードはぐんと上がるから」
僕:「えっ、それだけで?」
しおり:「うん。時間が限られてると、人は自然と工夫するからね。
“終わりが決まっている仕事”って、集中力とスピードの両方が上がるの」
僕:「ライブとか友達との予定がある日のほうが、サクッと仕事終わるのもそのせいか!」
しおり:「まさにそう。“すぐやる人”は、時間に区切りをつけて、意識的に集中を生み出してるんだよ」
やりたくないことは“断っていい”
本当にやりたいことだけやる働き方へ
僕:「“すぐやる”の話を聞いてると、なんか気が重くなることもあるんだよね…」
しおり:「それ、やりたくないことに“すぐやれ”って言われてる気がするからかもね」
僕:「あ…そうかも。正直、今の仕事ってあんまり好きじゃなくて…」
しおり:「千田さんも言ってたよ。**“やりたくないことを我慢して続けても、幸せにはなれない”**って」
僕:「でも、社会人って、やりたくないこともやるのが当たり前じゃ…?」
しおり:「もちろん全部を投げ出すわけじゃないよ。
でも、“これは本当に自分の人生に必要か?”って問い直すことは大事なんだ」
僕:「“断る勇気”って、すぐやる勇気と同じくらい大事なのかも…」
「すぐやる」は自分の人生を取り戻す力になる
しおり:「“すぐやる”って、単に仕事を早く終わらせる技術じゃなくて、
“自分の人生に必要なことを選び取る力”でもあるんだよ」
僕:「選び取る力…?」
しおり:「うん。“これはやりたい”と感じたことにすぐ動ける。
逆に、“これは違う”と思ったものはスッと手放す。
そうやって、“やりたい人生”に向かって自分でハンドルを握ることができるのが、“すぐやる人”なんだよ」
僕:「そっか。“すぐやる”って、自分を大切にする選択でもあるんだね」
しおり:「そう。“すぐやる力”は、自分の人生を取り戻すための、最初の一歩なんだよ」
まとめ|“すぐやる力”がくれる未来
✅ この記事のまとめ表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 評価と信頼 | すぐ動くことで「本気度」が伝わり、チャンスが舞い込む |
| 成果と効率 | スタートが早い人は、焦らず高品質な成果を出せる |
| 集中力の維持 | 未完了タスクを溜めないことで、脳が軽くなる |
| 質問力の向上 | 行動した人だけが、具体的で意味のある質問ができる |
| 決断力と信頼 | 即決できる人は信頼され、リーダーとしても評価される |
| 習慣化のコツ | 環境を整えることで、“すぐやる”は誰でも実現できる |
| 人生の主導権 | “すぐやる”は、自分の人生を取り戻す力になる |
💬しおりのラストメッセージ
しおり:「“あとでやろう”は、人生のブレーキ。
でも、“今やる”と決めたその瞬間から、人生は少しずつ動き出すよ」
しおり:「すぐやることは、才能じゃなくて“選択”なんだ。
選んだあなたは、すでに一歩前に進んでる。
焦らず、でも止まらずに。今日も、小さな一歩を踏み出していこうね」
📚書籍紹介
この記事は、千田琢哉さんの著書
『すぐやる力で差をつけろ』を参考にしました。
行動力を身につけて、人生を前に進めたい方におすすめの一冊です👇
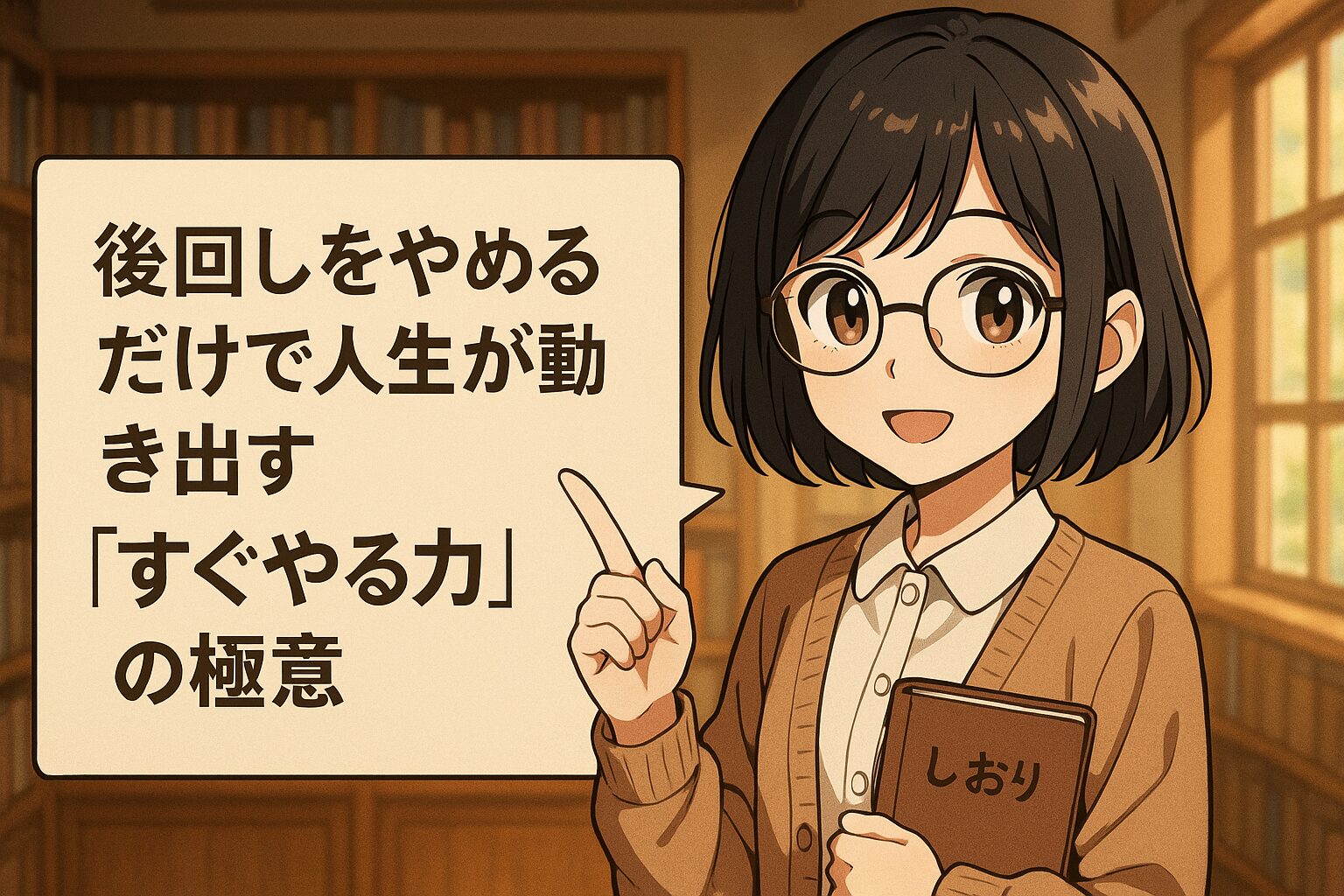


コメント