**しおりと僕の図書館相談〜本で紐解く人生のヒント〜**へようこそ📚
今回は、精神科医・宮口幸治さんの著書『ケーキの切れない非行少年たち』(新潮新書)を取り上げます。
この本は、医療少年院での勤務経験をもつ著者が、非行少年たちの「認知機能の弱さ」に着目し、なぜ彼らが何度も過ちを繰り返してしまうのか、その背景を明らかにした一冊です。
はじめに|「なぜ、あの子は繰り返すのか?」
僕: ニュースを見ててさ、「また少年が逮捕」って報道を目にするたびに、なんで何度も同じことを繰り返すんだろうって思っちゃうんだよね。
しおり: それ、実は“根っこ”にあるのは性格の問題じゃないかもしれないわよ。今日紹介するのは、精神科医・宮口幸治さんの著書『ケーキの切れない非行少年たち』。この本では、非行少年たちの多くが「軽度の知的障害」や「認知機能の弱さ」を抱えていることが明かされているの。
僕: えっ、ケーキを切れないってどういうこと…?
しおり: 一見普通に見える子でも、実は“見え方”“考え方”“感じ方”がまったく違っている。その結果、周囲とのズレが大きくなり、誤解され、排除され、非行へと追い込まれていくの。今回はそんな彼らの「脳の特性」と「社会とのミスマッチ」に迫っていくわよ。
非行少年たちの実情
僕: 非行少年って、単に素行が悪いだけじゃないの?
しおり: そう思われがちだけど、著者は医療少年院で多くの子どもたちを診てきて、驚くべき共通点を見つけたの。「認知機能が著しく低い」ってこと。
僕: つまり、見えてる世界が僕たちと違う…?
しおり: そう。例えば、会話がかみ合わない、図を見て写せない、ケーキを3等分できない…。それって単なる勉強不足じゃなく、脳の特性の問題なの。
世の中のすべてが歪んで見えている?
僕: 歪んで見えるって、比喩じゃなくて?
しおり: 比喩じゃなくて、ガチ。例えば「図を見てそのまま書き写して」と言っただけで、とんでもない形の絵が出てくる。つまり“見たものを正しく処理できない”んだよね。
僕: ええ…そりゃ話も通じないわけだ。
しおり: さらに、音も歪んで聞こえる可能性が高いって著者は言ってたわ。つまり「見えてない」「聞こえてない」から「分かってない」ってことなの。
ケーキを切れない子どもたち
僕: で、タイトルの“ケーキを切れない”って?
しおり: 「3人でケーキを分けて」って課題を出しても、まっすぐ線を引くだけで止まっちゃうの。ベンツのマークみたいに三等分できない。
僕: なるほど…それが“想像できない”ってことか。
しおり: そう。この子たちは「頭の中でイメージをつくる」ことが極端に苦手なの。
共通する6つの特徴
しおり: 非行少年たちに共通する特徴は、次の6つ。
- 見たり聞いたりして想像する力が弱い
- 感情のコントロールが苦手
- 思いつきで行動する
- 自分の問題点に気づけない
- コミュニケーションが苦手
- 力加減ができない
僕: ……あの、正直、身近にもこういう人いそう。
しおり: そう。だから「犯罪者=異常者」じゃなく、発見されなかった“支援が必要な人”ってこともあるの。
忘れられた存在「境界知能」
僕: 境界知能って、聞きなれないけど?
しおり: IQ70〜84のグレーゾーンにある人たちのこと。見た目は普通、会話もできる。でも、学習や仕事になると支障が出る。そのせいで、支援から漏れがちなの。
僕: 見過ごされる理由、そこか…。
しおり: 日本には約1700万人もいると言われてるのよ。けっして他人事じゃないわ。
働けない、続かない現実
僕: そういう人たちって、社会に出たらどうなるの?
しおり: 仕事が覚えられない、人間関係が続かない、出勤できない…で、1ヶ月以内に辞めてしまうケースも多いの。
僕: 負のループだ…。
しおり: そう。そして、お金も仕事もないから「闇バイト」などに流されて、再び犯罪に…という流れが生まれてしまうの。
認知機能を鍛える“コグトレ”とは?
僕: じゃあ、どうすれば?支援ってどんなことができるの?
しおり: 著者が開発したのが「コグトレ」っていう認知機能を鍛えるトレーニング。見る・数える・移す・覚える・想像する…など、脳の基礎体力を育てるの。
僕: いきなり道徳を教えるんじゃなくて、“学ぶ力”そのものを育てるんだね。
しおり: その通り。早ければ小学校低学年から始められるし、大人になってからでも効果はあるの。
まとめ:支援が間に合えば、未来は変えられる
僕:
今日の話、本当に考えさせられたよ…。非行少年って、ただ「悪い子」なんじゃなくて、認知機能の問題を抱えていたり、孤立してたり、そもそも“見え方”が違っていたんだね。
しおり:
そう。だから「更生」や「反省」を求める前に、そもそも“正しく見て、正しく考える力”を育てる土台が必要なの。社会の枠に合っていない子を責めるのではなく、「合わない理由」を見つけて支援する視点が大切よ。
僕:
僕も、どこかで「ダメな子」ってラベルを貼ってた気がする…。でも、コグトレみたいな支援があるなら、もっと早く気づいてあげられたかもしれないよね。
しおり:
うん。この本のメッセージは「認知機能のトレーニングを早期に行えば、非行の予防にも繋がる」という点。つまり、“納税者”として自立できる未来を、社会がつくっていく余地はあるということ。
最後に:知ることは「やさしさ」の第一歩
しおり:
『ケーキの切れない非行少年たち』は、加害者とされる人たちが、同時に支援を受けられなかった“被害者”であることを教えてくれる一冊だったわね。
僕:
うん。今後、学校でも職場でも「なんか不器用な子だな」って感じたときに、ちょっとだけ相手の背景に目を向けられるようになりたいな。
しおり:
その視点があるだけで、きっと誰かの孤立を防げるはず。支援って、特別な専門家だけのものじゃないから。あなたの“気づき”が、未来の誰かを救うかもしれないのよ。
僕:
…なんか、今日の話は重かったけど、すごく心に残ったよ。ありがとう、しおり。
しおり:
こちらこそ。次回はもう少し軽いテーマにしようかしら?(笑)それじゃあ、また図書館で📚✨
📘 書籍リンク
『ケーキの切れない非行少年たち』(宮口幸治 著/新潮新書)
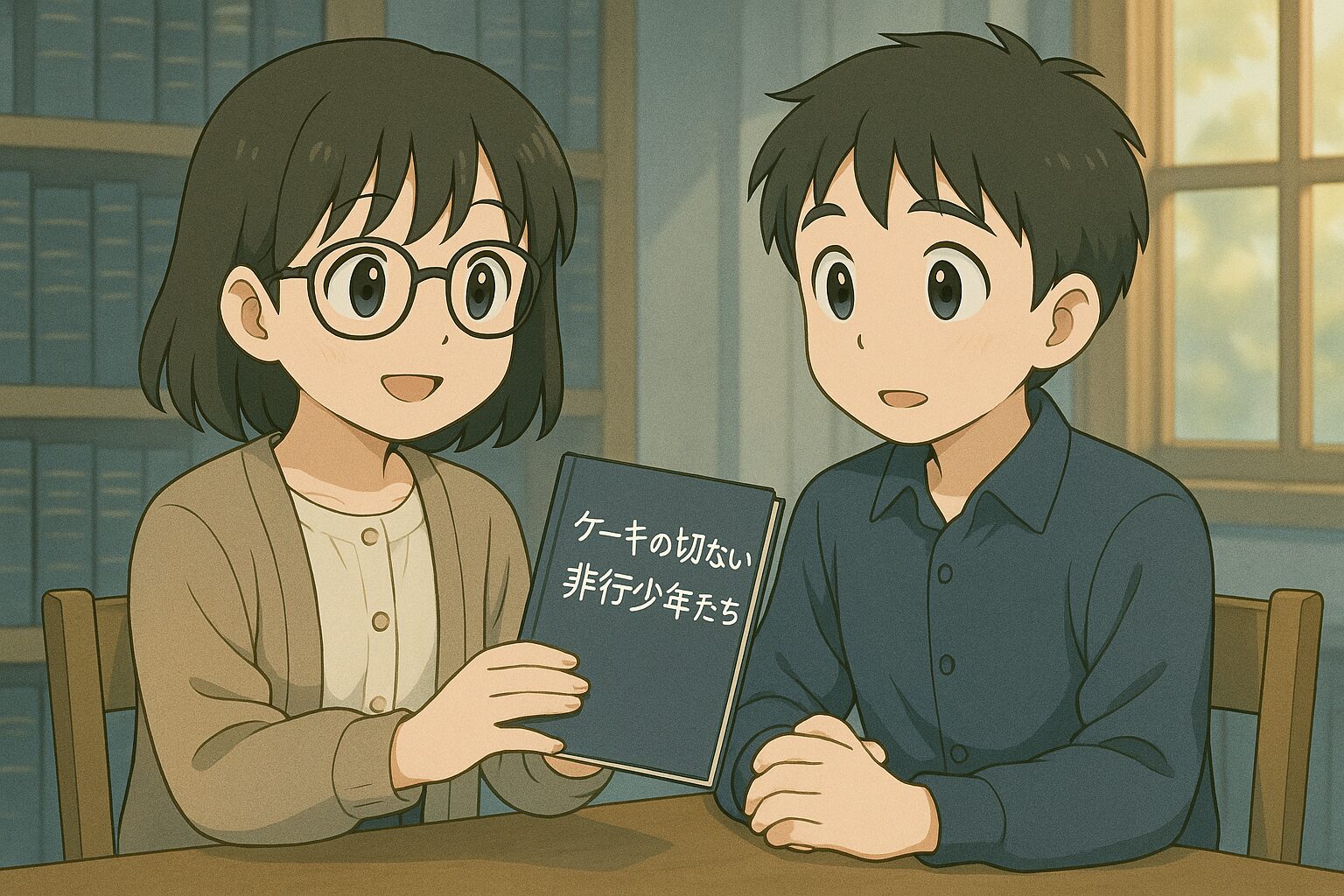


コメント